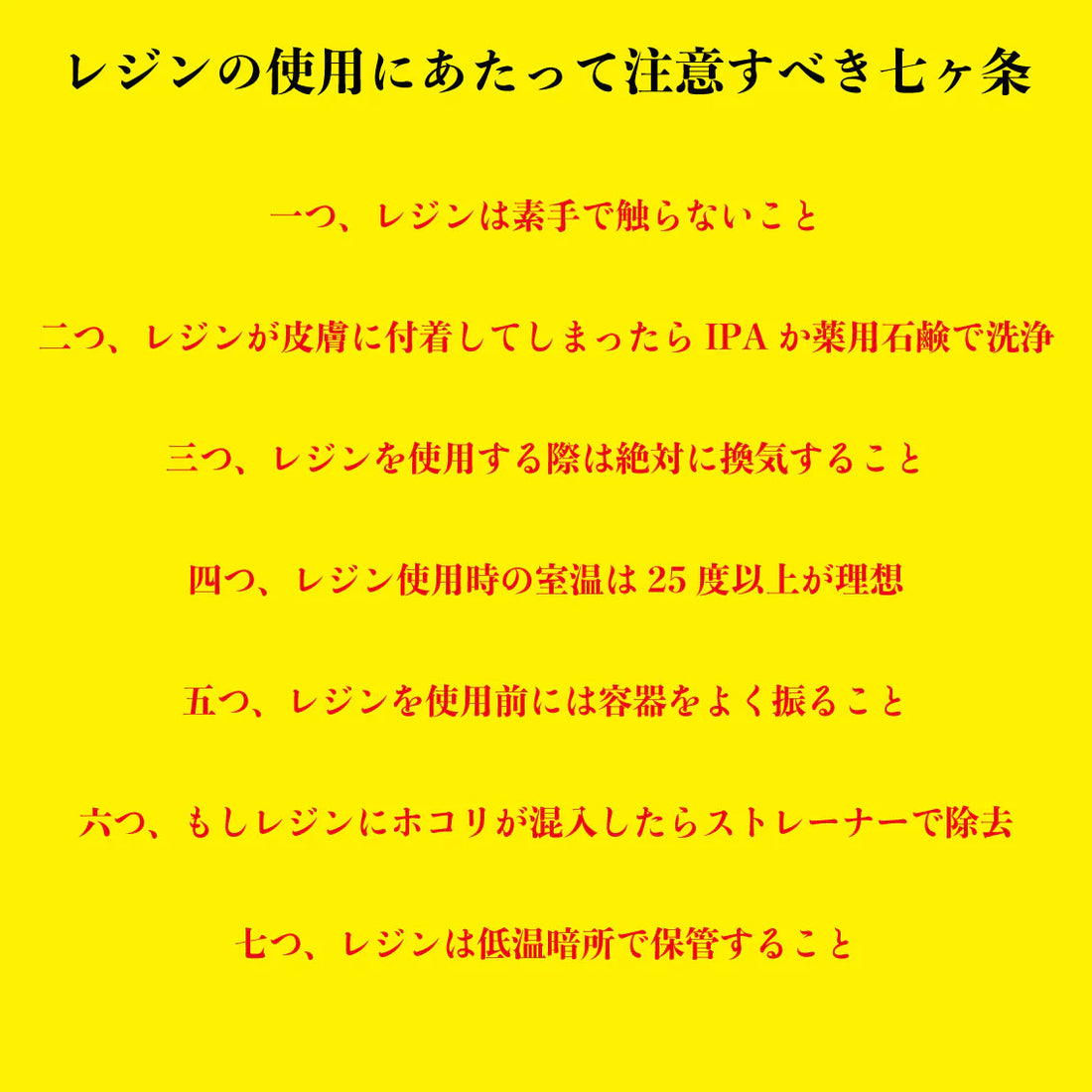動物福祉と3Dプリンター|ジレンマを超えてより豊かな世界へ
ヒューマニズムの歴史の行く先
ヒューマニズムは人類が発明したものの中で最も大きな発明品の一つだろう。
現在の我々に当たり前のように備わっている「人権」という理念もまた長い歴史の中で育まれてきたヒューマニズムの叡智に基づくものだ。もし、この「人権」がなければ、あらゆる権力の横暴に対して我々はたちまち無力になってしまう。理不尽な命令に対して我々が正義を持って反抗することができるということもまた、ヒューマニズムを背景にもつ「人権」が憲法上で保証されているからに他ならない。

人権の起源とも言われる12世紀「マグナ・カルタ」の写本
20世紀の歴史はこのヒューマニズムという思想が世界中に拡散した1世紀だったと言えるだろう。民主主義に基づかない独裁権力による圧政、奴隷労働や人種差別、子供差別やジェンダー差別など、世界が西洋によって近代化されていく中で発生した様々な不公正や不正義が、ヒューマニズムの名の下に少しずつ是正されていった。

閣僚たちと奴隷解放宣言の草稿を作るリンカーン大統領
やがて20世紀後半になると、ヒューマニズムの批判的精神はヒューマニズムそのものへも向けられていくことになる。ヒューマニズムを旗印に他国へと干渉し、その国の文化を簒奪するような先進国の振る舞いに対して、ヒューマニズムの視点から過去のヒューマニズムへと批判が加えられていくことになったのだ。そして近年、拡張したヒューマニズムはついにヒューマンの垣根さえも超えて、不公正の是正に乗り出そうとしている。そう、アニマルライツ(動物の権利)の回復だ。

動物の権利の思想的根拠として参照される『動物の解放』の著者ピーター・シンガー
人類はみな平等であり、生まれながらにして幸福を追求し、それを実現する権利を所有している。これこそがヒューマニズムが世界に広く知らしめた考えである。では、人間以外の動物はどうなのだろうか。彼らはその権利を所有していないのだろうか。それはヒューマニズムの歴史プロセスにおいて起こるべくして起こった当然の疑問だった。こうして、20世紀後半頃より動物の権利獲得を目指す運動が主に西欧を中心に広がっていくことになったのだ。
もちろん、アニマルライツを求める人々の中にも様々な立場がある。動物も人間も等しく生きている以上、全く同等の、かつ同様の権利が認められるべきだとする観点のもと、一切の畜産や屠殺、狩猟や肉食、動物園やペット飼育を否定するという立場。あるいは、これまでの長きに渡る肉食の歴史を踏まえて、食用としての畜産や屠殺、狩猟は認めつつも、そのあり方を少しでも動物にとって苦痛の少ない形にしていくことを目指すという動物福祉的な立場。
昨今では動物に法的人格を与え、裁判の原告となる権利を認める事例なども出てきており(実は動物のみならず川が裁判の原告になった事例もある)、アニマルライツは世界的にも極めて高い関心を集めている。かつて小説家のジョージ・オーウェルが『動物農場』に描いたような世界が、今まさに起こりつつあるということなのだ。

一方、こうしたアニマルライツを求める運動に対して批判的な意見を持つ人も少なくない。たとえば、市民的権利には市民的義務が伴うものであり、動物はその義務を果たすことができないというような意見や、人間のつくった尺度によって動物の幸不幸を判断したり、人間が作りだした「権利」という概念を動物に押し付けたりしていくような態度こそが傲慢であるというような意見などがそうだ。最もよく見られるのは、動物に権利があるなら植物にも権利があるはずだ、という主張だろう。つまり、際限なく権利の概念を拡張し続けていけば、やがては野菜を食べることすらできなくなるのではないか、という指摘だ。
あるいは日本においては世界の捕鯨反対運動に対する批判的な意見も多く見られる。捕鯨やイルカ漁は日本のローカルな文化の中に根差した伝統狩猟であり、そうした伝統的な文化を現代の価値観で安易に潰すべきではないという主張だ。この問題は度々世界でも取り上げられ、複数の視座からドキュメンタリー映画化も撮られている。特に鯨は哺乳類の中でも知能が高く、まだその巨大な体軀の持つ神秘的な性格から、動物愛護運動のメルクマールとなりやすいのだ。
推進派、反対派、どの立場の意見もきちんと追っていくと相応の理があるように感じられるが、そのぶん、この議論は落としどころの設定が難しい。近年では環境問題への関心の高まりから、平行線だった議論にやや波風が立っているとはいえ、この種のテーマはそれぞれの人生の根幹にある哲学の部分での対立を引き起こしてしまうため、社会全体のコンセンサスを得るということが達成しづらいのだ。
いずれにしても、筆者のような特別アニマルライツの運動と関わりを持たない人間にとってみても、先ほど紹介したアニマルライツの後者のような立場、つまり可能な範囲で動物が苦しむような機会は減らしたほうがいいという動物福祉的な考え方については、否定する余地がないように感じている。それこそペットを飼っている人なら、自分のペットと同種の動物が苦しむ姿を見るのは、人間が苦しむ姿を見るのと同様に心が痛くなるというもの。普段、食用にしている肉にしても、虐待的に飼育された動物の肉よりも、丁寧に飼育された動物の肉を食べたいと思ってしまうのが人情というものだろう(それはそれで都合の良い考えなのかもしれないが)。
↓ ショッキングな内容を含むため閲覧ご注意ください。
しかし、そうとはいえ、問題はそう簡単でもない。世界食糧機構のデータによれば、このままの勢いで人口が増え続け、なおかつその人口が現在の先進国と同等の食肉を消費した場合、明らかに食肉不足が起こることがすでに指摘されている。そもそも畜産のプロセスにおいて虐待的な状況が発生してしまう背景には食肉の大量生産大量消費の問題があるということを鑑みれば、世界の人口増加は動物福祉の状況をますます悪化させていく可能性があるのだ。
あるいは、今回のコロナ禍における急速なワクチン開発のように、医科学の領域で新薬などを開発する際には、これまで動物を用いた生体実験が多く行われてきている。言ってしまえば、人間に投与する前段階の毒味役として、動物の命がリスクに掛けられてきたということだ。一方で、ならば医科学の進歩を否定して、今後は新薬開発を行わないという選択が妥当かと言えば、それもまた余りに反動的だろう。このように、動物福祉を向上させていこうとする上でも問題は山積しており、一見それらは解決不能のようにも見えるのだ。
あっちの道へ行ってもダメ、こっちの道へ行ってもダメ。そのような場合、考えうるのは今までに発見されていなかった新たな道を探ることだろう。第三の道、そう、テクノロジーだ。
中でもこの困難な状況下において、人類が抱えている諸課題をクリアしつつ、同時に動物福祉の向上へとも繋がりうる道筋を示しているテクノロジーがある。他でもない3Dプリンターだ。
3Dプリンターは食肉産業に抜本的な変化をもたらす
動物福祉の向上に関して、3Dプリンターはすでに様々な形でオルタナティブな可能性を切り拓いてきた。
まずは当メディアでも幾度も紹介してきた3Dプリント・オルトミートだ。オルトミートとは要するに、実際の動物がとれたものではない人工培養食肉のことだが、現在、このオルトミートの製造の多くはバイオ3Dプリンターで行われているのだ。
代表的なところでは、イスラエルのベンチャーであるRedefineMeatやスペインのNOVA MEATなどが開発している3Dプリントミートがある。NOVA MEATが開発する「STEAK2.0」は、エンドウ豆や海藻、ビートルートなどを原材料に、顕微鏡レベルで植物由来のタンパク質を調整することで食肉の食感を再現しており、その出来栄えの見事さは広く知られている。味としても植物性でありながら、なんら本物の肉と遜色がないというレベルまできているらしく、徐々にではあるがすでにレストランなどへの提供も始まっているようだ。

NOVA MEATがプリントした「STEAK 2.0」
もちろん、動物性のオルトミートの3Dプリントも進められている。たとえば2021年、日本の大阪大学と弘前大学が和牛の幹細胞を使ってサシまで再現した3Dプリント和牛を開発したというニュースが世界的にも大きく話題になった。単に食肉不足を補うという観点のみならず、食の楽しみとしての部分の追求も行なっているあたりに、質にこだわる日本らしい心意気を感じざるを得ない。

現状、3Dプリントミートで報道されているものの多くは牛肉を模したものではあるが、一方で3Dプリントシーフードの開発も進められているようだ。2021年にはRevo Foodsが開発した植物性の3Dプリントサーモンの試食会が実際に開催され、話題を呼んだ。instagramに流れている写真などを見る限り、その見た目は本物のサーモンと見分けがつかない。味に関してもレビューを見る限りでは上々のようだ。

Revo Foodsの3Dプリントサーモン
米国サンディエゴのBlueNaluという企業もまた3Dプリントシーフードの開発を進めている。こちらでは植物性ではなく魚介類の幹細胞を用いたジューシーな3Dプリントシーフードの製造が目指されている。さらには豚肉や鶏肉などその他の食肉の3Dプリンティングも多くの企業、多くの研究チームによって研究開発が進められており、そう遠くない未来、あらゆる食肉が3Dプリントによって再現される日が来ることは間違いないだろう。
これらの取り組みは来たる食糧危機を主な問題意識として進められているものだが、当然、オルトミートの拡充は畜産業界への負担を大幅に減らすことになる。つまり、無理して大量の動物を飼育し、大量の食肉を生産する必要がなくなるのだ。おそらく、オルトミートが一般化した暁には、リアルミートは高価な贅沢品となっていく。そうして消費量が下がっていけば、飼育もまた動物福祉に配慮しつつ丁寧に行うことが可能になる。つまり、3Dプリント・オルトミートは、食肉不足と動物福祉の間のジレンマを解決する、現状で唯一と言っていい希望の道なのだ。
3Dバイオプリンターが動物実験を終わらせる
医療分野における動物福祉の向上に関しても3Dプリンターの存在が鍵となっている。
先述した通り、新薬の臨床試験に際した動物実験は、ライフサイエンスを何十年も悩ませてきた倫理的な問題だった。そもそも動物実験の必要性を支えていたのは、サリドマイド禍など過去の人間を対象とした臨床実験における悲惨な薬害事件への反省からだ。1964年に世界医師会が採択したヘルシンキ宣言は、ヒューマニズムの精神に基づいて人間を対象とした医学研究の安全性を高めることを目的として行われた高潔なものであり、日本もまたヘルシンキ宣言に則り、これまで環境省が定める基準の範囲内においてのみ動物実験を行なってきている。
とはいえ、そのさなかにも、人間都合で動物を利用することに対して迷いが生じなかったわけではない。実際、その倫理的な問題意識から、生きた動物を実験に用いることを段階的に廃止する動きが各国で見られており、すでに41カ国以上の国でその慣行を制限または禁止する法律が可決されている。大手製薬企業を複数擁する米国もまたその流れに追随しており、現在、動物実験をこれまで以上に制限していく方向へと議論が進められているようだ。
もちろん、これらの制限はただ闇雲に、つまり理想主義的に行われているわけではない。制限が可能になりつつある背景には人体の安全性確保のための動物実験を代替する方法が徐々に生まれてきているというライフサイエンスの技術的発展がある。その中でも重要な技術的発展の一つが3Dバイオプリンティング技術だ。この3Dバイオプリント技術によって、人間や動物の生体を用いず、しかし生きた細胞、生きた臓器、生きた皮膚を用いた実験が可能になったのだ。
たとえばインドのスタートアップ企業であるNext Big Innovation Labs (NBIL) は、ヒトの皮膚のバイオプリンティング技術により、人体や動物を用いない臨床試験の可能性を開拓している。人間の皮膚組織のサンプルから皮膚細胞を抽出、、そこに独自のバイオインクを混合し、皮膚組織をバイオプリント、これを発売前の化学薬品や化粧品、医薬品の検査に使用する。この方法ならばもしなんらかの副作用などがあっても、人間にも動物にも害が及ぶことはない。
あるいは米国ノースカロライナ州にあるウェイクフォレスト再生医療研究所 のアンソニー・アタラ氏は、薬剤の毒性をテストするための新しい多臓器チップを開発している。アタラ氏が発表した2020年2月の論文によると、「チップ上の3Dボディ」は、市場に参入した後に薬剤を回収するリスクを減らすだけでなく、より迅速で経済的な薬剤開発につながる可能性がある」とのことだ。
この「チップ上の3Dボディ」とは、多臓器の身体を単純化したモデルを極小のチップ上に再現したもので、様々な種類、用途の薬剤を反応を調べたい臓器ごとに反応を試験するためのコストを大幅に下げる可能性を秘めたものだと言われている。実際、この3DボディはすでにCOVID-19の研究にも使用されている。重要なことは、この実験が動物モデルを使った実験よりもはるかに役立つ可能性があるということ。また、それが事実ならば、これ以上、薬剤開発のために動物実験を行う必要がなくなることを意味しているのだ。
技術とともにジレンマを超えて
以上は、動物福祉向上の観点から、食と医療に関する3Dプリント技術の貢献を要約したものだが、上記したような技術がより広まっていけば、確実に動物に苦しみを与えねければならない機会自体が減少していく。なおかつ、これらの技術は来たる食糧不足問題にとっても、一筋の光芒を差し入れている。また今後の医療技術の継続的発展の上でも、何かを差し引くことなく、ポジティブな作用をもたらしていくだろう。
ヒューマニズムが直面している様々な矛盾を例に挙げ、斜に構えた態度でヒューマニズムを否定するのは簡単だ。確かに急進的なヒューマニズムは時に現実を無視する形で過去の伝統を破壊していく側面もなくはない。とはいえ、今日の我々が当たり前のように自ら職業を選び、パートナーを選び、選挙に行って投票することができるという恩恵にあやかっているのは、ヒューマニズムと人権思想の支えによるものであることも忘れてはいけないだろう。
おそらく、動物福祉もまた歴史的必然として人類が取り組まなければならない課題なのだ。その際、単に「自分たちの豊かさを我慢する」という方法を選ぼうとしてもうまくはいかない。動物福祉の課題を一つの創造のきっかけとし、人類が動物と共により豊かな生を送ることができる道を模索していった方が現実的だ。その上で重要なことは、今の手持ちのカードだけで考えすぎないことかもしれない。まだ手中には収まっていない未知のカードに、ジレンマから抜け出すためのアリアドネの糸が描かれているかもしれないのだ。
人類が新しいカードを引いてくるためにもテクノロジーの進歩が欠かせない。当メディアとしては3Dプリント技術が今後ますますこの地球上を生きる全ての生の支えとなっていくことを願うばかりだ。